もくじ
◆ はじめに|自宅で叶える、たったひとつの“はじまりの記録”

待望の赤ちゃんの誕生。
小さな手、小さな足、柔らかい頬――生まれて間もない新生児期の1ヶ月は、まさに“命が育まれる”奇跡のような時間です。
この時期の赤ちゃんは、1日ごとに顔つきが変わったり、眠り方や手足の動かし方も少しずつ成長していきます。
だからこそ、「今この瞬間を、写真に残しておきたい」と感じるママ・パパはとても多いのではないでしょうか。
そんな想いを形にしてくれるのが「ニューボーンフォト」。
近年はプロのフォトグラファーに依頼するだけでなく、自宅で、家族の手で撮影するというスタイルも人気を集めています。
- 自宅だからこそ赤ちゃんもママもリラックスできる
- 自分のペースで、何度でもトライできる
- なにより「自分の手で撮った」という特別な思い出になる
このブログでは、初めてでも安心して取り組めるセルフニューボーンフォトの方法や準備、撮影のコツを、丁寧にお伝えしていきます。
家族の“はじまり”を、ぜひあなたの手で記録してみませんか?
プロに依頼したい方はこちらもご参考に!
>>生まれたての“今”を残すニューボーンフォト、愛おしい記録とその活かし方<<
◆ セルフ撮影に最適なタイミングを知ろう

ニューボーンフォトの撮影にもっとも適している時期は、生後5日〜14日頃までと言われています。
この時期の赤ちゃんは、まだお腹の中にいた頃の姿勢を保っていて、手足をきゅっと丸めて眠る姿がとても愛らしいのが特徴です。
また、睡眠時間が長く、ちょっとした動きや音にもあまり反応せず、スヤスヤ眠ってくれている時間が多いのもこの頃ならでは。自然な姿で撮影しやすく、やさしい表情をカメラにおさめるチャンスが増えます。
とはいえ、出産を終えたばかりのママの体調もとても大切です。無理のない範囲で、赤ちゃんとママにとってベストなタイミングを選びましょう。
- 妊娠中に「予定日+1週間」を目安に、セルフ撮影の仮日程を立てておく
- 出産後に赤ちゃんと自分の体調を見ながら、撮影日を確定する
- 撮影は1回30分〜1時間程度におさめ、複数日に分けてもOK
「ニューボーンフォト=生後2週間以内に絶対撮らなきゃ!」と焦らず、家族みんなのペースで取り組むことが一番大切です。
赤ちゃんの“今”を無理なく、でもしっかりと残せるよう、少しだけ準備をしておきましょう。
◆ 撮影前の準備で“7割”が決まる

セルフニューボーンフォトは、「撮影が始まる前の準備」でほぼ結果が決まると言っても過言ではありません。
赤ちゃんが心地よく過ごせる環境、ママやパパがスムーズに動ける段取り、そして撮影に使う道具の工夫――。これらをしっかり整えておけば、当日の撮影もグッとラクになります。
室温は赤ちゃんファーストで
新生児期の赤ちゃんは体温調節がとても未熟です。
おくるみ1枚や裸ん坊での撮影も多いため、**室温は26〜28℃**が理想的。夏場はクーラーの冷えすぎに注意し、冬場はヒーターで足元までしっかり温めて。
エアコンの風が直接赤ちゃんに当たらないよう、風向きの調整やブランケットの用意も忘れずに。
床が冷たい場合は、ヨガマットや厚めのバスタオルを敷いてから背景布を設置すると、保温とクッション性が高まって安心です。
光は自然光+カーテンでふんわり柔らかく
写真の印象を左右するのが「光」。
人工的な照明よりも、午前〜昼過ぎの自然光を活用するのが一番おすすめです。窓のそばに撮影スペースをつくり、レースのカーテンで日差しをやわらげると、赤ちゃんの肌がふんわり明るく写ります。
強い直射日光が差し込む場合は、白いシーツや模造紙を使って光を反射・拡散させる工夫を。影が強く出すぎるのを防ぎ、ナチュラルで優しい印象の写真になります。
赤ちゃんの「機嫌がいい時間帯」を狙って
赤ちゃんのご機嫌タイムは、撮影の仕上がりに直結します。
理想的なのは、授乳後・オムツ替え後のリラックスしているタイミング。お腹が満たされて、眠ってしまう直前やウトウトしている時がベストです。
眠っている間に撮影するのも◎。特に「くるまりポーズ」や寝姿を撮るときは、深い眠りのほうがポーズが安定して表情も穏やかになります。
ご機嫌が悪くなってしまったら、一度中断して抱っこタイムに。焦らず、赤ちゃんのペースに合わせて進めるのがポイントです。
段取りでママ・パパの負担も軽減
「赤ちゃんを寝かせてから準備を始める」では遅すぎます。
撮影セットやカメラの位置は事前に確認・テストしておくことが大切です。おくるみや衣装、小物もすぐ手に取れるように整えておきましょう。
また、可能であればパートナーや家族にも協力してもらい、赤ちゃんの見守り役と撮影役に分かれると、より安全でスムーズに進みます。
「機嫌が悪いときはまた別のタイミングで大丈夫」という気持ちで、家族みんなで楽しみながら準備する時間も、かけがえのない思い出になります。
◆最低限そろえておきたい撮影グッズ

セルフニューボーンフォトを成功させるために、特別な機材は必要ありません。
でも、少しの工夫と「あると便利なアイテム」をそろえることで、撮影のクオリティはぐっとアップします。
ここでは、初心者のママ・パパでも簡単に取り入れられる基本アイテムと、写真映えを叶える小物の選び方をご紹介します。
おくるみ・ブランケット
ニューボーンフォトで欠かせないアイテムといえば、おくるみ。
赤ちゃんをやさしく包み込むことで安心感を与えるだけでなく、くるまりポーズやシンプルな演出にぴったりです。無地のガーゼやリネン素材など、柔らかい色合いのものを選ぶと赤ちゃんの肌を引き立ててくれます。
ブランケットは、赤ちゃんの下に敷いたり、背景として使うのも◎。
柄がある場合はなるべく控えめなものを選び、主役である赤ちゃんが埋もれてしまわないように工夫しましょう。
赤ちゃんに直接触れるものは、肌触りの良さと清潔さを重視してください。
クッション・タオル
セルフ撮影では、赤ちゃんの体勢をしっかり支えるためのサポートも重要です。
ふかふかのクッションや丸めたバスタオルを背中や首の下に差し込むことで、自然な姿勢をキープできます。撮影中にグラつかないよう、安定性をよく確認してください。
また、敷物の下にクッション材を仕込んでおくと、体への負担を減らすことができます。
使うクッションやタオルも、色は白やベージュなど主張しすぎないものを選ぶと写真全体がまとまりやすくなります。
スマホ or カメラ:手持ちでもOK!
プロ用の一眼レフがなくても大丈夫。
最近のスマホカメラは高性能なので、ポートレートモードやHDR設定を活用すれば十分きれいに撮影可能です。できれば、グリッド表示をオンにして構図を整えやすくしておくのがおすすめです。
両手が空くように三脚やスマホスタンドがあると、ブレ防止にもなり安心。100均の簡易スタンドでもOKです。
室内の光量が少ない場合は、クリップ式のLEDライトを使うのも効果的。ただし直接赤ちゃんに向けず、壁に反射させて間接的に使うとやさしい印象になります。
小物・飾り
写真に「物語」や「季節感」をプラスしてくれるのが、小物類です。
例えばこんなアイテムが人気です。
- 木製のアルファベットブロック(名前のイニシャルを並べる)
- 月齢カード(“0ヶ月”や“Hello World”など)
- ドライフラワーや季節の造花(春なら桜、秋なら紅葉など)
- ファーストトイやぬいぐるみ(生まれて初めての“お友達”)
選ぶときは、サイズ感と色味のバランスが重要です。赤ちゃんよりも目立ってしまうような派手な色や大きなアイテムは避け、ナチュラルなものを選ぶと統一感が出ます。
身近なもので十分!代用アイデア
「そんなにたくさん用意できない…」という方もご安心を。
実は、撮影小物はおうちにあるもので代用できるものがたくさんあります。
- 背景布 → 白いシーツやカーテン
- レフ板 → 画用紙や白いダンボール
- クッション → 枕や折りたたんだブランケット
- 小物 → ママのヘアアクセサリーやベビーソックス
必要以上に揃えようとせず、「いま手元にあるものをどう活かすか」という視点で準備するのがおすすめです。
◆ 構図を決めて撮影スタート!

準備が整ったら、いよいよ撮影のスタートです。
でもいきなりシャッターを切るのではなく、「どんな写真を残したいか」というイメージを先に描いておくことが大切です。
赤ちゃんの魅力がいちばん引き立つ構図を選ぶことで、セルフでもプロ顔負けの一枚に仕上がります。
「くるまりポーズ」で王道ショット
はじめてセルフ撮影に挑戦するなら、赤ちゃんをおくるみで優しく包んだくるまりポーズがおすすめです。
丸くなった姿勢は、赤ちゃん自身も安心するだけでなく、新生児らしい「ふにゃっとした小ささ」や「柔らかさ」を感じられる構図になります。
撮影は真上から覗き込むように撮ると、バランスがとりやすく、背景とのコントラストもきれいに映ります。
おくるみの色や布の質感で雰囲気が変わるので、撮影前に何パターンか巻いてみるのもおすすめです。
ぐっすり眠っている時がシャッターチャンス。手足をしっかりおさめるか、あえて顔だけをメインにするかで印象が変わります。
手や足のアップで「小ささ」を引き立てる
赤ちゃんの「今だけの小ささ」は、全身だけでなく手足のパーツアップでも伝えることができます。
くしゃっとした手、ピンと伸びた足の指、くるんとした爪先…。どれも見ているだけで愛おしくなる一瞬です。
例えば、ママやパパの手と比べて撮ったり、結婚指輪を赤ちゃんの足の指に通して撮るのも人気のアイデアです。
小物を使わずとも、「手 × 光の陰影」だけでもアートのような1枚になります。
近くから撮るときは、ピントをしっかり合わせることがポイントです。スマホの場合はタップでピントを固定し、撮影前に数秒待ってブレを防ぎましょう。
家族の手を囲んで「つながり」を表現
赤ちゃん一人の写真だけでなく、ママ・パパ・兄弟姉妹の手で赤ちゃんを囲む構図も、とても人気があります。
「命を包み込む」ような印象になり、家族の絆や温かさが自然と伝わる一枚に仕上がります。
大きな手の中に収まった小さな手や足は、赤ちゃんの存在のかけがえのなさを感じさせてくれるはずです。
構図を考えるときは、真上から・斜め45度から・足元側からなど、カメラの角度を変えて試してみると、バリエーションが広がります。
兄弟姉妹とのツーショットで“成長の記録”に
もし上のお子さんがいる場合は、兄弟姉妹とのショットもぜひ撮影しておきましょう。
「初めて会ったときの記録」は、後から見返したときに家族みんなの宝物になります。
おすすめは、寝かせた赤ちゃんの隣に兄弟姉妹も寝てもらい、真上から撮る構図。
小さい兄弟姉妹であれば、一緒に並んで寝るだけでもかわいらしいですし、少し大きなお子さんなら赤ちゃんの頭に手を添えるポーズも素敵です。
恥ずかしがってしまう場合は、ぬいぐるみを使って一緒に撮るだけでもOK。
撮影が楽しい思い出になるよう、遊びの延長として声かけしてあげるのがコツです。
バリエーションを広げて、写真にストーリーを
1つの構図だけで終わらせず、少しずつ角度を変えたり、小物を追加してアレンジしてみましょう。
・同じポーズでおくるみの色を替える
・背景を違うブランケットに差し替える
・最初はアップ、次は全身…とズームを調整
たくさん撮って、後でベストショットを選ぶというスタイルが◎。
赤ちゃんの表情や動きは一瞬で変わるからこそ、多めに撮影することがセルフ撮影の鉄則です。
◆スマホでもOK!撮影テクニック

「カメラの知識がないからうまく撮れないかも…」
そんな心配はいりません。最近のスマホは、赤ちゃんの可愛さをしっかり引き出してくれる高性能な機能が充実しています。
ここでは、スマホ撮影でも十分きれいに仕上げるための基本テクニックと、初心者でもすぐに真似できる撮影のコツをご紹介します。
ポートレートモードで背景をやさしくぼかす
赤ちゃんをふんわりと引き立たせたいときに便利なのが、スマホのポートレートモード。
被写体(=赤ちゃん)にピントを合わせながら、背景を自然にぼかしてくれるため、プロが撮ったような奥行きのある写真になります。
背景がごちゃついていても、主役である赤ちゃんが際立つので、お部屋の生活感を隠したいときにも効果的です。
距離が近すぎると自動でピントが合いづらいので、少し離れてからズームして撮るのがコツです。
連写モードで「奇跡の1枚」を逃さない
赤ちゃんは突然手足を動かしたり、思いがけない表情を見せたりします。
そんな一瞬を確実に捉えるには、連写モードがとても便利。
1回シャッターを押すだけで何枚も撮れるため、後でゆっくり見返してベストショットを選ぶことができます。
機種によってはシャッター長押しで自動連写になりますので、事前に試しておくと安心です。
また、連写中はなるべくスマホを動かさないよう、両手でしっかり構えましょう。
AE/AFロックでピントと明るさを固定
「写真がブレてしまう…」「明るさが安定しない…」
そんなときに使いたいのが、スマホのAE/AFロック(露出・フォーカスの固定)機能です。
赤ちゃんの顔をタップして長押しすると、ピントと明るさが固定され、カメラの自動補正によるブレや暗さのムラを防げます。
光の強さに合わせて、上下スワイプで明るさを微調整できる機種も多いので、自分のスマホで試してみてください。
グリッド表示で構図バランスを整える
写真の仕上がりをぐっと引き締めてくれるのが、スマホのグリッド(3×3の線)表示。
赤ちゃんの顔や目が、画面の「交差点」にくるよう意識すると、構図に安定感が生まれます。
真ん中に収めるだけでなく、少しずらして「余白を活かす」構図もおしゃれ。グリッドを使うことで、バリエーションのある写真が簡単に撮れるようになります。
設定から「グリッドをオン」にするだけで使える機能なので、ぜひ活用してみてください。
手ブレ防止にはスタンドや台を活用
赤ちゃんの撮影中は両手がふさがることも多く、スマホを片手で持ちながらの撮影はどうしてもブレやすくなります。
そんなときは、三脚やスマホスタンドを使って固定するのがおすすめ。
100均や雑貨店で手に入る簡易スタンドでも十分ですし、なければ安定した箱やクッションの上にスマホを置いて代用するのもOK。
また、セルフタイマー(2〜3秒)を設定することで、シャッターを押すときの手ブレも防げます。
撮影後は「加工しすぎず、少し整える」がコツ
撮影後の写真は、加工アプリを使って少し明るさを整えたり、肌色をナチュラルに整えるだけで十分きれいに仕上がります。
あえて“そのまま”の赤ちゃんの表情を活かすのも、ニューボーンフォトの魅力です。
過度なフィルターや補正はせず、「色味をそろえる」「明るさを調整する」などの最低限の編集で、やさしい印象を大切に残しましょう。
スマホで上手に撮影する方法をもっと詳しく知りたい方はこちら!
>>スマホ写真が劇的に上達!初心者でも「プロっぽく」撮れる撮影テクとは<<
◆ 安全に撮るための4つの注意点

セルフでのニューボーンフォト撮影は、おうちで気軽に挑戦できる一方で、「赤ちゃんの安全を最優先に考える」ことが何よりも大切です。
生まれたばかりの赤ちゃんはとても繊細。だからこそ、小さな配慮や準備が、赤ちゃんの安心とママ・パパの自信につながります。
ここでは、撮影時にぜひ知っておいてほしい安全面での注意点を4つに絞ってご紹介します。
高い場所での撮影は避ける
見た目の演出を重視するあまり、ベッドの上やソファの端など、不安定な場所で撮影したくなることもあるかもしれません。
でも、赤ちゃんはいつどんなタイミングで手足を動かすか予測ができません。
撮影は必ず床の上で行うことを基本にしましょう。
マットや厚手のブランケットを重ねてクッション性を持たせ、赤ちゃんが万が一動いても安心できる環境を整えておくことが大切です。
また、床であってもカメラや小物を周囲に置くと転倒の原因になることがありますので、周囲の安全確認も忘れずに。
無理なポーズは絶対にさせない
SNSやプロの撮影例で見かけるような、手を頬に添えたポーズや、あごを乗せた状態で撮るポーズは、赤ちゃんにとって自然ではない体勢です。
こういったポーズは、専門的なトレーニングを受けたフォトグラファーが安全を確保したうえで、短時間で撮影しています。
セルフ撮影では、赤ちゃんが自然にとる姿勢のまま撮るのが一番安心で、結果的に赤ちゃんらしさが残る一枚になります。
首がすわっていない時期の赤ちゃんに対しては、特に首や頭が傾かないように支える工夫も必要です。
手足の可動域も大人の感覚と違うため、「この姿勢で大丈夫かな?」と感じたらすぐやめる判断も大切です。
撮影中は必ず大人2人以上で見守る
セルフ撮影といえども、1人での撮影は避けるのが理想です。
片方がカメラを構えたりセットを直したりしている間、もう1人が赤ちゃんのそばにいて体勢や呼吸を常に見守ることで、安全性がぐっと高まります。
パートナーや家族にお願いできる場合は、「赤ちゃんを見ててね」「手元に影がかかってないか見ててね」など、具体的な声かけをしながら役割分担をすると、撮影がよりスムーズになります。
どうしても1人で行う場合は、赤ちゃんのそばを離れないことを最優先にし、カメラの位置は事前に固定しておく、無理な構図は避けるなどの工夫をしましょう。
撮影時間は30分以内が目安
可愛い姿をたくさん残したいからといって、長時間の撮影は赤ちゃんにとって負担になります。
おくるみの締め付けやポーズ替えなど、少しずつ疲れやストレスがたまってしまうこともあります。
1回の撮影時間は30分以内を目安に、赤ちゃんの様子を見ながらこまめに休憩を取りましょう。
撮影を1日で終わらせる必要はありません。数日に分けて、毎日少しずつ撮るスタイルでも、結果的にたくさんの良い写真が残ります。
「今日はこの1カットだけでいいや」と思えるくらいの心の余裕が、赤ちゃんとの時間をより大切に感じさせてくれるはずです。
◆ 撮った写真を“カタチ”に残そう

セルフで撮影したニューボーンフォトは、ただスマホに保存するだけではもったいない――。
生まれたばかりの愛しい表情や小さな手足の記録を、“見返せるカタチ”にして残すことで、その瞬間はさらに深く、温かく記憶に残ります。
赤ちゃんの成長は驚くほど早く、数ヶ月後には「こんなに小さかったんだ」と驚く日がきっとやってきます。
だからこそ、今この瞬間を、手に取って眺められる形にしておくことが、家族にとってかけがえのない宝物になるのです。
おすすめ① アクリルフォトスタンド
お気に入りの1枚を、透明感のあるアクリル素材でスタイリッシュに飾れるアイテム。
どんなインテリアにも馴染みやすく、リビングや寝室にさりげなく飾ることで、赤ちゃんが家族の“まんなか”にいることを実感できる存在になります。
おすすめ② キャンバスパネル・ウッドフォト
柔らかい風合いのキャンバス地や、あたたかみのある木材にプリントされた写真は、まるでアートのような仕上がり。
おうちの中に飾るだけでなく、毎年の記念フォトとしてシリーズ化していくのも人気です。
年月が経つほどに味わいが増し、家族のストーリーを積み重ねていけるのも魅力です。
おすすめ③ キーホルダー・マグカップなど日常使いのアイテム
毎日手に取るものに赤ちゃんの写真があると、それだけで心がふっと和みます。
マグカップやキーホルダーなどの小物にすれば、祖父母や親戚へのプレゼントにも◎。
特に初孫の場合、「見せる写真」ではなく「使う写真」として贈れるので、サプライズ感も喜びもひとしおです。
おすすめ④ フォトアルバムにまとめて保存
写真が複数枚あるなら、1冊のアルバムにしてまとめておくのもおすすめです。
成長の過程をストーリーのように並べれば、「自分だけの育児絵本」のような一冊になります。
ページの余白にメッセージを書いたり、そのときの気持ちを添えておけば、将来赤ちゃんが大きくなったときに読み返して感動してくれるかもしれません。
このように、“今だけ”の写真を「記録」ではなく「記憶」として深く残す方法はたくさんあります。
そしてどの形も、赤ちゃんの存在を身近に感じられる温かなギフトになります。
オリジナルグッズを簡単に1つから作成できるBONATHIAはこちら
◆ まとめ|大切な一瞬を、自分の手で残そう

赤ちゃんの新生児期は、あっという間に過ぎてしまいます。
だからこそ、「今」の姿を写真に残しておくことは、未来への大切な贈りものになります。
セルフでのニューボーンフォトは、特別な道具や技術がなくても大丈夫。
愛情をこめて撮るその1枚には、きっと家族だけの温もりが宿ります。
ママやパパ自身の手で、赤ちゃんの“はじまり”を記録してみませんか?
その写真は、これからの毎日をもっとやさしく、あたたかくしてくれるはずです。
【ブログをご覧いただいてる方に特別クーポン】

BONATHIAで使用できるクーポンおひとり様1回限りと記載お願いします。
クーポンコード
2000円以上の購入でで300円オフ
5X5IZPMT
クーポンコード
5000円以上の購入でで500円オフ
WZQB1AJY
自分の「好き」を、もっと気軽に広げよう!
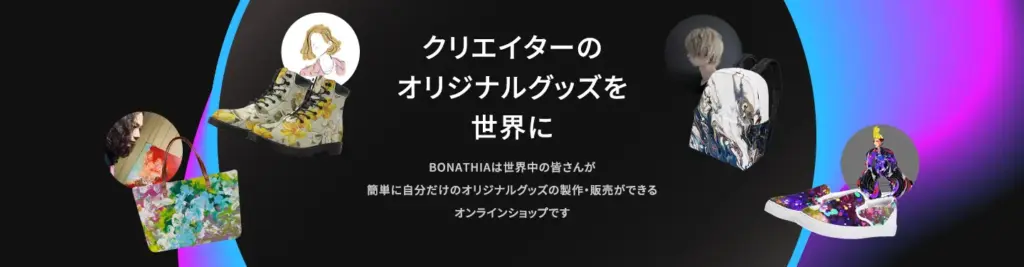
オリジナル商品を販売しているまたはしようとしているあなたにとって、
「在庫リスクゼロ」で「自由度の高い」販売スタイルを実現してくれる救世主「BONATHIA」
BONATHIAはデザイン性 × 使いやすさ × 集客力の3拍子が揃ったサービスです。
✅ 在庫なしで商品数を増やしたい
✅ 手間をかけずにショップ運営したい
✅ もっと自由に、自分らしいグッズを届けたい
そんな方には、BONATHIAがおすすめ!